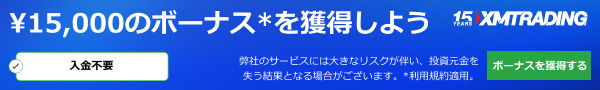--- ここから先は会員限定 ---
このコンテンツは会員専用です。閲覧にはログインが必要です。
まだ会員登録がお済みでない方は、以下のリンクからXMの取引口座開設後、下記の新規ユーザー登録をお願いします。
※当サイトの会員登録には、当サイト経由で開設したXMの取引口座番号が必要です。既にXM口座を開設の方は追加で口座を開設してください。
現在新規口座を開設するだけで13,000円の取引ボーナスが付与されます。
XMの新規登録や追加口座の開設は、下記リンクよりお手続きいただけます。
【パートナーコードJDFYG】
XM口座開設はこちら
日銀会合後に示した日本円の動向と今後のアジア通貨の鍵

概要 日本円の動向とインフレデータの影響 日本円はインフレ率上昇を背景に一時的に反発しましたが、日銀の金融政策が現状維持を続けるとの見通しから、円安傾向が続いています。消費者物価指数(CPI)の上昇は日銀の政策変更への期待を一部高めたものの、上田総裁の慎重な姿勢が円高への持続的な効果を抑えています。 ドル高トレンドと円安圧力 米連邦準備制度理事会(FRB)の高金利維持方針や、ドルの安全資産としての地位がドル高を支えています。この結果、日米金利差が広がり、円安が進行しています。特に、FRBの利下げペース鈍化観測がドルの強さを助長しています。 政府の為替介入への期待とアジア通貨全体の弱含み 急激な