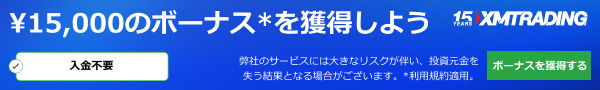--- ここから先は会員限定 ---
このコンテンツは会員専用です。閲覧にはログインが必要です。
まだ会員登録がお済みでない方は、以下のリンクからXMの取引口座開設後、下記の新規ユーザー登録をお願いします。
※当サイトの会員登録には、当サイト経由で開設したXMの取引口座番号が必要です。既にXM口座を開設の方は追加で口座を開設してください。
現在新規口座を開設するだけで13,000円の取引ボーナスが付与されます。
XMの新規登録や追加口座の開設は、下記リンクよりお手続きいただけます。
【パートナーコードJDFYG】
XM口座開設はこちら
USD/JPYの最新動向とトレーダーが注目すべきポイント

概要 USD/JPYの動向と影響要因 米国雇用統計(NFP)や日銀の金融政策など、USD/JPYは多くのファンダメンタルズ要因によって動きます。特に、米国の利上げ期待や日本の超低金利政策、地政学リスクが市場の変動要因として注目されています。 テクニカル分析の重要性 サポートラインやレジスタンスライン、移動平均線、RSIなどのテクニカル指標を活用することで、トレンドの方向性を判断し、リスクを管理しやすくなります。特に、重要ラインの突破や反発に注目することが推奨されます。 トレード戦略と今後の見通し 短期トレードでは経済指標発表後の急な値動きを活用し、長期トレードでは日米金利差や政策変動の可能性を